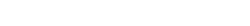太ってきたなと思ったら糖質制限ダイエットをするのは当たり前とされ、市民権を得たと思います。
それでも、まだまだ糖質制限に否定的な人は多く、特に有名大学の先生ほど、「そんなことやったらダメだ。死にたいのか」と強い口調でやめさせようとしていますね。ネットの記事でも、糖質制限を否定しているものは、有名大学の先生のように権威がある人ばかりが書いている印象です。
糖質制限は水分だけが抜けるとまだ言ってる
糖質制限が話題になり始めた2010年代は、糖質制限で痩せるのは水分が抜けるからだという人が多かったですが、今でも、そう言っている先生がいます。
ブドウ糖(糖質)を体内に蓄えるためには、グリコーゲンという形にして肝臓や筋肉に貯蔵します。その際、ブドウ糖の3倍とか4倍とかの水分が必要になりますが、グリコーゲンをエネルギー使用して消費した場合には、その水分も一緒に失われます。
糖質制限をすると、外からのブドウ糖補給が断たれるので、このままでは低血糖になってしまいます。でも、肝臓に蓄えたグリコーゲンをブドウ糖に戻し、血中に放り込めば血糖値を上げることができますから低血糖になりません。
肝臓に蓄えられるグリコーゲンは100グラム程度ですから、それを使い切ると、300グラムから400グラムの水分も失われます。だから、糖質制限で痩せるのは、肝臓に蓄えたグリコーゲンと水分を合わせても、せいぜい500グラムという計算です。なお、筋肉に蓄えたグリコーゲンは血糖値の上昇に使えないので、糖質制限をしたからといって血糖値を維持するためにそれを取り崩すようなことはありません。運動をして筋肉のグリコーゲンが消費された後にできる乳酸からブドウ糖を作り出すことはありますけどね。
どうも、有名大学の先生は、この辺を理解していないような気がするんですよね。
白米は脂肪にならないとか怪しい理論
また、やたらと白米を食べることを推奨するのも、有名大学の先生の特徴。
白米を食べても脂肪にならないとか、糖質が脂肪に変わるのはネズミの実験結果であって人間には当てはまらないとか、ここまで言い出すと本当に大学の先生なのかと疑ってしまいますよ。
糖質を食べたら血糖値が上がり、インスリンが分泌されてブドウ糖(糖質)が中性脂肪となって脂肪組織に蓄えられることは、栄養学、生理学、生化学の本に書いてあること。先生の言っていることが事実なら、これらの内容を大幅に書き換えなければなりません。
また、糖質制限をしてグリコーゲンがなくなると、今度は筋肉を分解してブドウ糖を作り出す糖新生で血糖値を維持し始めるから、糖質制限を続けるほど筋肉が痩せ細るとも言っています。確かに糖新生の材料にタンパク質が使われますが、中性脂肪や乳酸も糖新生の材料となるので、いきなり筋肉を減らして糖新生に充てることは考えられません。
他に糖質制限ダイエットは糖尿病患者の食事であって、健常者がやると寿命が縮むとものたまっています。いや、健常者の寿命が縮むんなら糖尿病の方の寿命だって縮むでしょう。
もう、むちゃくちゃ。
権威ある人が言うと、信じる人が増えるんですから、せめて生理学や生化学を無視した発言はやめていただきたいですね。